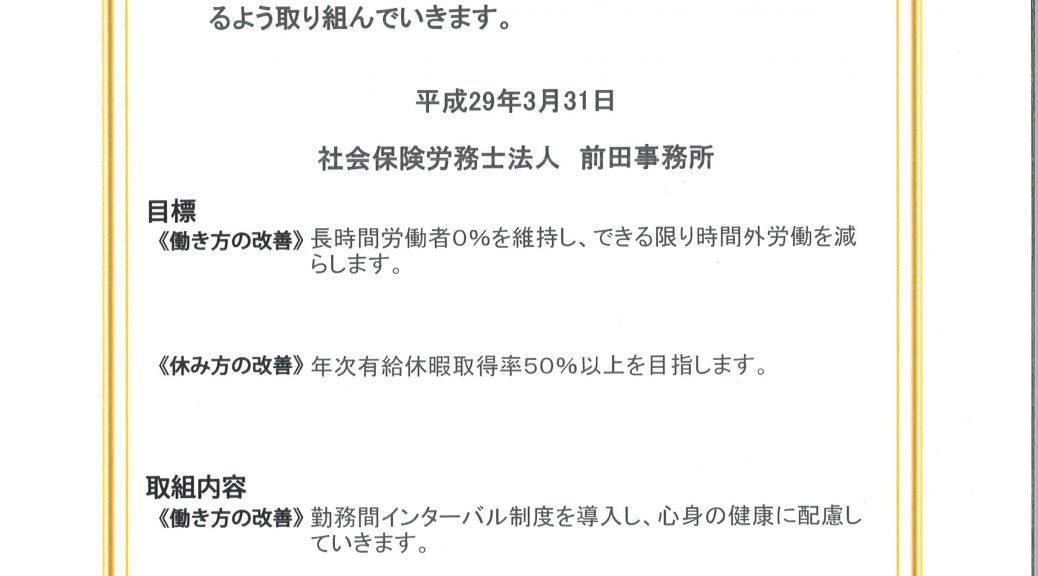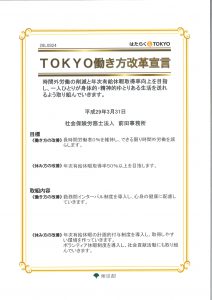The post 第353話「春闘賃上げ5.25%」 appeared first on 日本人事総研.
maeda_editor のすべての投稿
第352話「管理職目指したい59%」
第352話「管理職目指したい59%」
The post 第352話「管理職目指したい59%」 appeared first on 日本人事総研.
第351話「大学生5割AI利用」
第351話「大学生5割AI利用」
The post 第351話「大学生5割AI利用」 appeared first on 日本人事総研.
第350話「都内倒産13%減129件」
第350話「都内倒産13%減129件」
The post 第350話「都内倒産13%減129件」 appeared first on 日本人事総研.
第349話「中高進学、生活費削るが6割」
第349話「中高進学、生活費削るが6割」
The post 第349話「中高進学、生活費削るが6割」 appeared first on 日本人事総研.
第348話「特定技能退職者1年以内66%」
第348話「特定技能退職者1年以内66%」
The post 第348話「特定技能退職者1年以内66%」 appeared first on 日本人事総研.
第347話「ベースアップ デフレ下では抑制的」
第347話「ベースアップ デフレ下では抑制的」
The post 第347話「ベースアップ デフレ下では抑制的」 appeared first on 日本人事総研.
第346話「都内女性社長比率9.1%」
第346話「都内女性社長比率9.1%」
The post 第346話「都内女性社長比率9.1%」 appeared first on 日本人事総研.
第345話「中堅企業数2割増目標」
第345話「中堅企業数2割増目標」
The post 第345話「中堅企業数2割増目標」 appeared first on 日本人事総研.
第344話「賃上げ企業61.9%ある」
第344話「賃上げ企業61.9%ある」
The post 第344話「賃上げ企業61.9%ある」 appeared first on 日本人事総研.
第343話「後継者不在51.1%」
第343話「後継者不在51.1%」
第342話「企業の2025年卒採用の充足率」
第342話「企業の2025年卒採用の充足率」
第341話「中小企業の半数が賃上げを予定」
第341話「中小企業の半数が賃上げを予定」
第340話「友人との関わり、対面重視?」
第340話「友人との関わり、対面重視?」
第339話「退職代行サ-ビス」
第339話「退職代行サ-ビス」
第338話「通勤時間もタイパ意識」
第338話「通勤時間もタイパ意識」
第337話「女性管理職、1割超」
第337話「女性管理職、1割超」
第336話「従業員代行で退職9%」
第336話「従業員代行で退職9%」
第335話「高齢者最多3625万人」
第335話「高齢者最多3625万人」
第334話「持てる子の数、0~1が56%」
第334話「持てる子の数、0~1が56%」
第333話「転職で賃金増、最多36%」
第333話「転職で賃金増、最多36%」
第332話「若者の収入不安4.5ポイント改善」
第332話「若者の収入不安4.5ポイント改善」
第331話「インタ-ン8割が参加」
第331話「インタ-ン8割が参加」
第330話「社長の能力定義開示2割」
第330話「社長の能力定義開示2割」
第329話「2024年入社の初任給、大卒、高卒で4%超上昇」
第329話「2024年入社の初任給、大卒、高卒で4%超上昇」
第328話「社長の平均年齢60歳」
第328話「社長の平均年齢60歳」
第327話「チャンスあれば転職」
第327話「チャンスあれば転職」
第326話「大卒就職内定率98.1%」
第326話「大卒就職内定率98.1%」
第325話「賃上げ率5%未満が6割」
第325話「賃上げ率5%未満が6割」
第324話「中小の6割以上が人手不足」
第324話「中小の6割以上が人手不足」
第323話「中小賃上げ32年ぶり高水準」
第323話「中小賃上げ32年ぶり高水準」
第322話「物流業界の2024年問題」
第322話「物流業界の2024年問題」
第321話「賃上げ率4%超か」
第321話「賃上げ率4%超か」
第320話「中小61%賃上げ予定」
第330話「社長の能力定義開示2割」
日本企業で経営者の能力をまとめた「スキルマトリックス」の充実が課題となっている。
日本の上場企業400社のうち、能力の定義まで示した企業は2割に留まった。
企業統治助言のHRガバナンス・リーダ-ズが国内外の主要上場企業について2023年時点の開示内容を調べた。
日本ではJPX日経インデックス400の397銘柄、米国ではS&P500のうち時価総額上位109社が対象となった。
スキルマトリックスは経営陣、取締役などのもつ能力や経験を一覧にしたもの。
取締役の選任を諮る株主総会に向け、招集通知で記載される。
日本企業では97%(387社)が社長や最高経営責任者(CEO)など経営トップのスキルを公開していた。
開示する企業の数自体は米国の92%を上回る。
焦点となるのは開示の内容。
スキルの定義や選定理由まで説明する企業は米国で65%に達するのに対し、日本は21%に留まる。
スキルや経験と、経営戦略の関係を具体的に説明する企業は米国で89%、日本は15%だった。
米国企業では経営陣に必要とされる能力を明確に定義し、職歴などに沿って説明する 傾向が強い。
以上
第329話「2024年入社の初任給、大卒、高卒で4%超上昇」
民間シンクタンクの産労総合研究所は、2024年4月に入った新入社員の大卒初任給は前年より4.01%高い22万6341円だったと発表した。
上昇率は1991年の5.2%以来の高い水準になった。
大卒初任給の伸びは22年まで1%を下回って推移していたが、23年は2.84%まで高まった。
高卒の初任給も24年は上昇率が4%を超えた。
初任給を引き上げた理由を複数回答で聞いたところ、「人材を確保するため」(81.8%)が最も多く、「在籍者のベ-スアップがあったため」(37.4%)が続いた。
産労総研では「人手不足を背景に、他社よりも高い水準に設定する企業が増えている」と分析している。
以上
第328話「社長の平均年齢60歳」
帝国デ-タバンクの調査によると、2023年12月時点での東京都の企業の社長平均年齢は60.0歳だった。
前年を0.2歳上回り、比較できる過去33年間で最高を更新した。
50歳以上が占める割合は79.6%で5年前より3.3ポイント上昇しており、中小企業の事業承継問題は深刻化している。
約147万社を収録している企業デ-タベースから帝国デ-タが集計、分析した。
社長平均年齢を業種別でみると「製造」が62.9歳で最も高く、IT(情報技術)企業が分類される「サービス」が57.2歳と最も低かった。
帝国デ-タは今回の調査を踏まえて、「社長の高齢化が進めば、体調不良など不測の事態が生じる可能性は高まる」と早めの事業承継対策の必要性を指摘している。
以上
第327話「チャンスあれば転職」
東京商工会議所の調査によると、2024年度新入社員に就職先の会社にいつまで働きたいかとの問いで「チャンスがあれば転職」との回答が23年度比6.4ポイント増の26.4%となり、調査記録が残る1998年度以来最高となったことがわかった。
「定年まで働きたい」の21.1%(23年度から3.3ポイント低下)を上回り、長期勤続志向の低下があらわになった。
就職活動が「順調だった」「ほぼ順調だった」は合計で66.2%とコロナ禍以降で最も高かった。
人手不足を背景に売り手市場だったことが背景にあるとみられる。
社会人生活で不安に感じていることでは「仕事が自分の能力や適性に合っているか」(48.9%)、「上司・先輩・同僚と上手くやっていけるか」(42.8%)が上位にあがった。 配属や上司は選べず運任せという意味の「配属ガチャ」「上司ガチャ」を懸念しているようだ。
以上
第326話「大卒就職内定率98.1%」
文部科学省などの調査によると今年春に、大学(学部)を卒業した学生の今年4月1日時点での就職内定率は、98.1%で前年と比べて0.8ポイント上昇し、調査が始まった1996年度以降で過去最高となった。
短期大学や高等専門学校を加えた「大学等」も98.1%で前の年と比べて0.6ポイント上昇し、2番目に高い水準となった。
また、高校生の就職率も98%で、調査が始まった1976年以降で4番目に高い水準だった。
この結果について文部科学省は「調査対象の大学へヒアリングをしたところ、深刻な人手不足の影響で昨年より企業の求人が増加し、売り手市場となっていることが要因と考えられる。新型コロナの影響もほとんどないと無いと聞いている」としている。
以上
第326話「大卒就職内定率98.1%」
文部科学省などの調査によると今年春に、大学(学部)を卒業した学生の今年4月1日時点での就職内定率は、98.1%で前年と比べて0.8ポイント上昇し、調査が始まった1996年度以降で過去最高となった。
短期大学や高等専門学校を加えた「大学等」も98.1%で前の年と比べて0.6ポイント上昇し、2番目に高い水準となった。
また、高校生の就職率も98%で、調査が始まった1976年以降で4番目に高い水準だった。
この結果について文部科学省は「調査対象の大学へヒアリングをしたところ、深刻な人手不足の影響で昨年より企業の求人が増加し、売り手市場となっていることが要因と考えられる。新型コロナの影響もほとんどないと無いと聞いている」としている。
以上
第325話「賃上げ率5%未満が6割」
帝国デ-タバンクが発表した2024年の賃上げ実績に関する調査結果によると、賃上げ率5%未満が調査対象企業の6割を超え、連合が掲げている「5%以上」の目標を下回る企業が半数以上を占めた。3%台が最多の2割で「据え置き」との回答も2割弱あった。
回答企業の9割弱は中小企業で、高い賃上げを実施した大企業との給与格差が広がる懸念がある。
調査は4月5日~15日までインタ-ネットで実施、1050社から回答を得た。うち、中小は87%を占める920社だった。同時期に実施した調査は今回が初めてで過去との比較デ-タはない。
全体では77%の企業が賃上げを実施していた。中小に絞って賃上げ率の分布をみると、最多は3%台で22.3%を占めた。次に多かったのが、据え置きで17.1%だった。5%未満の合計で68.2%に上った。一方、6%以上とした企業も12.3%あった。
製造業では従業員数が20人以下などの小規模に絞ると、据え置きが最多の27.7%だった。
以上
第325話「賃上げ率5%未満が6割」
帝国デ-タバンクが発表した2024年の賃上げ実績に関する調査結果によると、賃上げ率5%未満が調査対象企業の6割を超え、連合が掲げている「5%以上」の目標を下回る企業が半数以上を占めた。3%台が最多の2割で「据え置き」との回答も2割弱あった。
回答企業の9割弱は中小企業で、高い賃上げを実施した大企業との給与格差が広がる懸念がある。
調査は4月5日~15日までインタ-ネットで実施、1050社から回答を得た。うち、中小は87%を占める920社だった。同時期に実施した調査は今回が初めてで過去との比較デ-タはない。
全体では77%の企業が賃上げを実施していた。中小に絞って賃上げ率の分布をみると、最多は3%台で22.3%を占めた。次に多かったのが、据え置きで17.1%だった。5%未満の合計で68.2%に上った。一方、6%以上とした企業も12.3%あった。
製造業では従業員数が20人以下などの小規模に絞ると、据え置きが最多の27.7%だった。
以上
第324話「中小の6割以上が人手不足」
日本商工会議所などか実施した「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」によると、人手が「不足している」と回答した企業の割合が65.6%に上り、3社に2社が人手不足という厳しい状況が浮き彫りとなった。
業種別では、「建設業」が78.9%、「運輸業」77.3%、「介護・看護業」76.9%と8割近くに達した。最も低い「製造業」でも57.8%となっており、人手不足は幅広い業種の課題となっている。
人手不足への対応方法としては、「採用活動の強化(非正規社員も含む)」が81.8%と最も多かった。採用だけでなく省力化や多様な人材の活用などの取り組みが求められているが、「事業のスリム化、ムダの排除、外注の活用」は39.1%だった。
以上
第324話「中小の6割以上が人手不足」
日本商工会議所などか実施した「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」によると、人手が「不足している」と回答した企業の割合が65.6%に上り、3社に2社が人手不足という厳しい状況が浮き彫りとなった。
業種別では、「建設業」が78.9%、「運輸業」77.3%、「介護・看護業」76.9%と8割近くに達した。最も低い「製造業」でも57.8%となっており、人手不足は幅広い業種の課題となっている。
人手不足への対応方法としては、「採用活動の強化(非正規社員も含む)」が81.8%と最も多かった。採用だけでなく省力化や多様な人材の活用などの取り組みが求められているが、「事業のスリム化、ムダの排除、外注の活用」は39.1%だった。
以上
第323話「中小賃上げ32年ぶり高水準」
連合が4月4日に発表した賃上げの集計結果(2日午前10時時点)は、組合員が300人に満たない中小企業の賃上げ率が前年同期比1.27ポイント高い4.69%だった。
中小企業の春闘は通常、大手の労使交渉が妥結する3月中旬以降に本格化する。比較的規模が大きい企業から合意に至るため、集計の回数を重ねるごとに賃上げ率は低下する傾向がある。ただ、今回発表した3回目の集計は前回の水準を0.2ポイント程上回った。
高水準の背景には人手不足がある。連合の芳野友子会長は「中小規模の事業者は人手不足の問題が非常に大きい。人材流出を食い止めるために、賃上げが必要だという認識があるのではないか」と説明する。
しかしながら、中小企業を取り巻く環境は明るくなく、原材料や人件費の増加分を巡る取引先との協議が難航しているケ-スが多い。「中小の賃上げは取引先が値上げを受け入れてくれるかどうかにかかっている」「毎日コスト削減につながる方法を考えているが無い袖はふれない」との声も多い。
城南信用金庫(東京都品川区)は、3月中旬に東京都と神奈川県の顧客約800社を対象に賃上げの意向を調べたところ、「賃上げする」と答えたのは36%にとどまり、「予定なし」は3割を超えた。川本恭治理事長は「賃上げしたくても、ほとんどの会社が価格転嫁できておらず原資がなく、できないのが実態だ」と説明する。
以上
第323話「中小賃上げ32年ぶり高水準」
連合が4月4日に発表した賃上げの集計結果(2日午前10時時点)は、組合員が300人に満たない中小企業の賃上げ率が前年同期比1.27ポイント高い4.69%だった。
中小企業の春闘は通常、大手の労使交渉が妥結する3月中旬以降に本格化する。比較的規模が大きい企業から合意に至るため、集計の回数を重ねるごとに賃上げ率は低下する傾向がある。ただ、今回発表した3回目の集計は前回の水準を0.2ポイント程上回った。
高水準の背景には人手不足がある。連合の芳野友子会長は「中小規模の事業者は人手不足の問題が非常に大きい。人材流出を食い止めるために、賃上げが必要だという認識があるのではないか」と説明する。
しかしながら、中小企業を取り巻く環境は明るくなく、原材料や人件費の増加分を巡る取引先との協議が難航しているケ-スが多い。「中小の賃上げは取引先が値上げを受け入れてくれるかどうかにかかっている」「毎日コスト削減につながる方法を考えているが無い袖はふれない」との声も多い。
城南信用金庫(東京都品川区)は、3月中旬に東京都と神奈川県の顧客約800社を対象に賃上げの意向を調べたところ、「賃上げする」と答えたのは36%にとどまり、「予定なし」は3割を超えた。川本恭治理事長は「賃上げしたくても、ほとんどの会社が価格転嫁できておらず原資がなく、できないのが実態だ」と説明する。
以上
第322話「物流業界の2024年問題」
2019年に施行された働き方改革関連法案の際に特例で適用されていた時間外労働の猶予が終わり、4月から年間960時間の上限が課せられる。
物流各社は人手不足が慢性化しており、十分な運転手を確保できず安定的な長距離輸送が困難になることが課題となっており、現状の物流システムや労働環境のまま輸送を維持するためには運転手の増員が必要になる。
全日本トラック協会の調査(2022年)によると、時間外労働が960時間を超える運転手がいると回答した企業は27.1%とおよそ4社に1社以上だった。
野村総合研究所は、このままの状態では2025年に全国の荷物の28%、30年には35%を運べなくなる可能性があるとの試算を公表している。 物流各社は、配送方法の見直しや荷下ろし作業の効率化、運転手の負担軽減などの対応は待ったなしとなっている。
以上
第322話「物流業界の2024年問題」
2019年に施行された働き方改革関連法案の際に特例で適用されていた時間外労働の猶予が終わり、4月から年間960時間の上限が課せられる。
物流各社は人手不足が慢性化しており、十分な運転手を確保できず安定的な長距離輸送が困難になることが課題となっており、現状の物流システムや労働環境のまま輸送を維持するためには運転手の増員が必要になる。
全日本トラック協会の調査(2022年)によると、時間外労働が960時間を超える運転手がいると回答した企業は27.1%とおよそ4社に1社以上だった。
野村総合研究所は、このままの状態では2025年に全国の荷物の28%、30年には35%を運べなくなる可能性があるとの試算を公表している。 物流各社は、配送方法の見直しや荷下ろし作業の効率化、運転手の負担軽減などの対応は待ったなしとなっている。
以上
第321話「賃上げ率4%超か」
「今年は昨年以上の熱量と決意をもって、物価上昇に負けない賃金引上げを目指す」。
経団連の十倉雅和会長は2024年の賃上げを巡る春季労使交渉が本格スタ-トした1月の労使フォーラムで方針を示した。
経団連の集計によると、23年の春季労使交渉での大手企業の平均賃上げ率は3.99%だった。
昨年9月の懇談会で十倉会長が示した「4%超」とする水準は実現すれば1922年以来となる。
後に「数字ありきではない」と事実上撤回したが、24年に4%を超える水準を達成できるかは、日本の30年デフレ脱却の是非を占う一つの焦点となる。
野村証券の1月中旬時点の集計によると、23年11月以降の賃上げ表明は大企業を中心に約30社にのぼり23年の同時期の10社弱を上回る水準で推移する。
日本は30年に及びデフレ下で、従業員の雇用を優先したことも賃上げの停滞に拍車をかけた。
主要国の約20年の賃金水準の変化を購買力平価ベ-スで比較すると、米国が1.3倍、韓国が1.5倍に伸びるなか、日本はほぼ伸びていない。
足元で物価高が続き、賃金上昇が追いついていない。物価を考慮した実質賃金は23年12月まで21カ月連続でマイナスが続く。物価高を克服するには継続的な賃上げが欠かせない。国内の雇用者数の7割を占める中小の賃上げも課題となる。
連合は5%以上の賃上げを要求している。00年代以降は22年まで1%台~2%台前半の低水準だった。2年連続で3.5%を超えれば、およそ30年ぶりとなる。3月13日の集中回答の結果に注目が集まる。
以上
第321話「賃上げ率4%超か」
「今年は昨年以上の熱量と決意をもって、物価上昇に負けない賃金引上げを目指す」。
経団連の十倉雅和会長は2024年の賃上げを巡る春季労使交渉が本格スタ-トした1月の労使フォーラムで方針を示した。
経団連の集計によると、23年の春季労使交渉での大手企業の平均賃上げ率は3.99%だった。
昨年9月の懇談会で十倉会長が示した「4%超」とする水準は実現すれば1922年以来となる。
後に「数字ありきではない」と事実上撤回したが、24年に4%を超える水準を達成できるかは、日本の30年デフレ脱却の是非を占う一つの焦点となる。
野村証券の1月中旬時点の集計によると、23年11月以降の賃上げ表明は大企業を中心に約30社にのぼり23年の同時期の10社弱を上回る水準で推移する。
日本は30年に及びデフレ下で、従業員の雇用を優先したことも賃上げの停滞に拍車をかけた。
主要国の約20年の賃金水準の変化を購買力平価ベ-スで比較すると、米国が1.3倍、韓国が1.5倍に伸びるなか、日本はほぼ伸びていない。
足元で物価高が続き、賃金上昇が追いついていない。物価を考慮した実質賃金は23年12月まで21カ月連続でマイナスが続く。物価高を克服するには継続的な賃上げが欠かせない。国内の雇用者数の7割を占める中小の賃上げも課題となる。
連合は5%以上の賃上げを要求している。00年代以降は22年まで1%台~2%台前半の低水準だった。2年連続で3.5%を超えれば、およそ30年ぶりとなる。3月13日の集中回答の結果に注目が集まる。
以上
第320話「中小61%賃上げ予定」
日本商工会議所は4月以降に賃上げを予定する企業が61.3%に上り、うち36.3%は「3%以上」の賃上を計画しているとの調査結果(全国中小約6,000社から49.7%の回答率)を発表した。
深刻な人手不足を背景に、中小でも高い賃上げ意欲が広がっている状況が明らかになった。
賃上げ実施予定企業の割合は、前年同期より3.1ポイント増えた。
業績改善がない中で賃上げを実施するとの回答は60.3%で、前年同期より1.9ポイント減少した。
減少傾向が続いていることから、日商では価格転嫁による業績改善が少しずつ進んでいるとみている。
賃上げ率の見通しについては、「5%以上」との回答が10%で、「4%以上5%未満」が9.3%、「3%以上4%未満」が17.3%と続いた。
賃上げ方法(複数回答)は、定期昇給が前年同期比5.7ポイント減の70.4%だった一方、基本給を底上げするベ-スアップは8.3ポイント増の49.1%で全体的な底上げを目指す動きが出ている。
賃上げ実施について「未定」と回答した企業は34.7%だった。
以上
第320話「中小61%賃上げ予定」
日本商工会議所は4月以降に賃上げを予定する企業が61.3%に上り、うち36.3%は「3%以上」の賃上を計画しているとの調査結果(全国中小約6,000社から49.7%の回答率)を発表した。
深刻な人手不足を背景に、中小でも高い賃上げ意欲が広がっている状況が明らかになった。
賃上げ実施予定企業の割合は、前年同期より3.1ポイント増えた。
業績改善がない中で賃上げを実施するとの回答は60.3%で、前年同期より1.9ポイント減少した。
減少傾向が続いていることから、日商では価格転嫁による業績改善が少しずつ進んでいるとみている。
賃上げ率の見通しについては、「5%以上」との回答が10%で、「4%以上5%未満」が9.3%、「3%以上4%未満」が17.3%と続いた。
賃上げ方法(複数回答)は、定期昇給が前年同期比5.7ポイント減の70.4%だった一方、基本給を底上げするベ-スアップは8.3ポイント増の49.1%で全体的な底上げを目指す動きが出ている。
賃上げ実施について「未定」と回答した企業は34.7%だった。
以上
第319話「正社員の人手不足52.1%」
中堅・中小企業を中心に人手不足が深刻さを増している。
帝国デ-タバンクの調査によると、正社員が不足していると感じている企業は2023年10月時点で前年同月比1.0ポイント高い52.1%となった。
10月としては2018年に次いで過去2番目の高水準。
業種別では訪日客が回復している「旅館・ホテル」などで人員圧迫が目立つ。
旅館・ホテルは人手不足と回答した割合が前年比10.2ポイント高い75.6%で、日本政府観光局によると10月の訪日客数は251万6500人と2019年の同月を0.8%上回った。
観光需要は回復が目立つ一方、コロナ禍での離職者が多く人手の確保が追いつかない状況が続いている。
デジタル化による生産効率向上を図る企業が増えるなか、「情報サ-ビス」も人手不足との回答が3.8ポイント増えて72.9%だった。
エンジニアの採用競争は一段と激しくなっている。
今春の残業規制の厳格化による影響が懸念されている建設や物流もそれぞれ7割近くが不足感を訴えた。
人手不足は中堅・中小には事業継続に関わる問題。
帝国デ-タバンクの調査では、2023年1月~10月の人手不足による企業の倒産件数は前年同期比78%増の206件となり、集計値がある2014年以降の年間最多件数を上回った。
以上
第319話「正社員の人手不足52.1%」
中堅・中小企業を中心に人手不足が深刻さを増している。
帝国デ-タバンクの調査によると、正社員が不足していると感じている企業は2023年10月時点で前年同月比1.0ポイント高い52.1%となった。
10月としては2018年に次いで過去2番目の高水準。
業種別では訪日客が回復している「旅館・ホテル」などで人員圧迫が目立つ。
旅館・ホテルは人手不足と回答した割合が前年比10.2ポイント高い75.6%で、日本政府観光局によると10月の訪日客数は251万6500人と2019年の同月を0.8%上回った。
観光需要は回復が目立つ一方、コロナ禍での離職者が多く人手の確保が追いつかない状況が続いている。
デジタル化による生産効率向上を図る企業が増えるなか、「情報サ-ビス」も人手不足との回答が3.8ポイント増えて72.9%だった。
エンジニアの採用競争は一段と激しくなっている。
今春の残業規制の厳格化による影響が懸念されている建設や物流もそれぞれ7割近くが不足感を訴えた。
人手不足は中堅・中小には事業継続に関わる問題。
帝国デ-タバンクの調査では、2023年1月~10月の人手不足による企業の倒産件数は前年同期比78%増の206件となり、集計値がある2014年以降の年間最多件数を上回った。
以上
第318話「創業10年の日本企業の成長は遅い」
情報処理推進機構(IPA)が企業向けのソフトウエアを開発・販売する新興企業を対象にした調査(米国261社、日本135社から回答)によると、創業10年以上の米国ソフトウエア振興企業のうち、上場直前の「レイタ-期」(事業が拡大し持続的なキャッシュフロ-がある)まで成長した企業が7割に上ったことがわかった。
一方で日本は3割にとどまった。
米国企業は柔軟に事業モデルを変換するのに対し日本企業は消極的である点が成長スピ-ドの差につながっているようだ。
環境変化などに合わせた事業モデルの変換を行ったとする米国企業は、創業初期の「シード期」からレイタ-期の4期間の平均で94%を占めた。
対して、日本企業は同50%だった。
事業モデルを変換した理由(複数回答可)を聞くと、米国企業では「他社との競争激化」が52%で最多だった。
海外に比べ日本の起業家はリスクを避ける傾向にあるとする業界の声は多い。
だが、競争に対応するための大きな変革も受け入れなければ、その先の成長機会は望めない。
日本でもクラウド経由でソフト提供する「SaaS」企業が増えるなか、米国に見習うことは多くありそうだ。
以上
第318話「創業10年の日本企業の成長は遅い」
情報処理推進機構(IPA)が企業向けのソフトウエアを開発・販売する新興企業を対象にした調査(米国261社、日本135社から回答)によると、創業10年以上の米国ソフトウエア振興企業のうち、上場直前の「レイタ-期」(事業が拡大し持続的なキャッシュフロ-がある)まで成長した企業が7割に上ったことがわかった。
一方で日本は3割にとどまった。
米国企業は柔軟に事業モデルを変換するのに対し日本企業は消極的である点が成長スピ-ドの差につながっているようだ。
環境変化などに合わせた事業モデルの変換を行ったとする米国企業は、創業初期の「シード期」からレイタ-期の4期間の平均で94%を占めた。
対して、日本企業は同50%だった。
事業モデルを変換した理由(複数回答可)を聞くと、米国企業では「他社との競争激化」が52%で最多だった。
海外に比べ日本の起業家はリスクを避ける傾向にあるとする業界の声は多い。
だが、競争に対応するための大きな変革も受け入れなければ、その先の成長機会は望めない。
日本でもクラウド経由でソフト提供する「SaaS」企業が増えるなか、米国に見習うことは多くありそうだ。
以上
第317話「Z世代、テレワ-ク実施49%」
不動産サ-ビス大手のコリア-ズ・インタ-ナショナル・ジャパンが東京23区内に正社員として勤務する「Z世代」(18~27歳/825人)のテレワ-ク実施状況まとめによると、週1回以上のテレワ-クをしている割合は49.8%だった。
子どもがいる人に限ると実施率は79.8%。週2~3日の頻度で実施は61.8%だった。
テレワ-クの頻度を「増やしたい」もしくは「どちらかというと増やしたい」と回答したのは49.8%で、今のテレワ-ク・出社頻度を「維持したい」は27.9%だった。
テレワ-クをする理由(複数回答)では「通勤時間がもったいない」が56.0%で最も多く、「会社の方針」が28.5%と続いた。
同社では「Z世代はタイパ(タイムパフォ-マンス)良く仕事したいという意識が高く、他の世代よりテレワ-ク志向が強い」と分析している。
働きたいオフィス街のある駅を聞いたところ東京駅が25.0%で最も高く、大手町駅19.3%、有楽町駅11.6%と続いた。「若者の街」のイメージが強い渋谷は3.4%で全体 の11番目だった。
以上
第317話「Z世代、テレワ-ク実施49%」
不動産サ-ビス大手のコリア-ズ・インタ-ナショナル・ジャパンが東京23区内に正社員として勤務する「Z世代」(18~27歳/825人)のテレワ-ク実施状況まとめによると、週1回以上のテレワ-クをしている割合は49.8%だった。
子どもがいる人に限ると実施率は79.8%。週2~3日の頻度で実施は61.8%だった。
テレワ-クの頻度を「増やしたい」もしくは「どちらかというと増やしたい」と回答したのは49.8%で、今のテレワ-ク・出社頻度を「維持したい」は27.9%だった。
テレワ-クをする理由(複数回答)では「通勤時間がもったいない」が56.0%で最も多く、「会社の方針」が28.5%と続いた。
同社では「Z世代はタイパ(タイムパフォ-マンス)良く仕事したいという意識が高く、他の世代よりテレワ-ク志向が強い」と分析している。
働きたいオフィス街のある駅を聞いたところ東京駅が25.0%で最も高く、大手町駅19.3%、有楽町駅11.6%と続いた。「若者の街」のイメージが強い渋谷は3.4%で全体 の11番目だった。
以上
第317話「Z世代、テレワ-ク実施49%」
不動産サ-ビス大手のコリア-ズ・インタ-ナショナル・ジャパンが東京23区内に正社員として勤務する「Z世代」(18~27歳/825人)のテレワ-ク実施状況まとめによると、週1回以上のテレワ-クをしている割合は49.8%だった。
子どもがいる人に限ると実施率は79.8%。週2~3日の頻度で実施は61.8%だった。
テレワ-クの頻度を「増やしたい」もしくは「どちらかというと増やしたい」と回答したのは49.8%で、今のテレワ-ク・出社頻度を「維持したい」は27.9%だった。
テレワ-クをする理由(複数回答)では「通勤時間がもったいない」が56.0%で最も多く、「会社の方針」が28.5%と続いた。
同社では「Z世代はタイパ(タイムパフォ-マンス)良く仕事したいという意識が高く、他の世代よりテレワ-ク志向が強い」と分析している。
働きたいオフィス街のある駅を聞いたところ東京駅が25.0%で最も高く、大手町駅19.3%、有楽町駅11.6%と続いた。「若者の街」のイメージが強い渋谷は3.4%で全体 の11番目だった。
以上
第316話「景気回復する9割」
読売新聞社が、主要企業の経営トップ30人を対象に、「新春・景気アンケ-ト」を行ったところ9割近い26人が「回復する」と回答し、世界経済の減速懸念などで落ち込んだ前年より増えた。
今後半年程度の景気について、回復を見込む26人が「緩やかに」を選び、「急速に」の回答はなかった。
「足踏み状態になる」は3人で、「緩やかに悪化する」が1人だった。
回復の要因を複数回答で聞いたところ、22人が「個人消費の回復」を挙げ、「訪日客(インバウンド)消費の拡大」(15人)、「設備投資の回復」(14人)、「雇用改善、賃金の上昇」(13人)などの内需が景気のリ-ド役になることへの期待が高まった。
足踏み状態となる要因としては、「中国経済の低迷」、「個人消費の低迷」が挙がった。
現状の景気については「緩やかに回復」が22人、「足踏み状態にある」が8人だった。
以上
第315話「チャットGPT、就活生も利用」
スカウト型就活サイトを手掛けるベネッセi-キヤリア(東京・新宿)によると、大学3~4年の4人に1人が就職活動において米オープンAIの対話型生成AI「Chat GPT」を活用した経験があることがわかった。
調査はスカウト型就活サイト「dodaキャンパス」に登録する大学3~4年生452人から回答を得た。
チャットGPTを活用したことがあると答えた人は26.5%だった。
活用の具体例を複数回答で尋ねたところ「企業の志望動機の作成」が63.6%と最も多かった。
活用した理由(複数回答)は「企業分析やエントリ-シ-ト(ES)作成などの作業時間短縮」(60%)や「今後のキャリアや自己分析などの思考整理の時間短縮」(45.8%)が上位を占めた。
活用して感じたメリットとデメリットについても複数回答で聞いた。
「自分でも思いつかない気づきが得られた」が77.5%と一定の効果を得られた考える学生が多かった。
一方で、活用していないと回答した学生は73.5%に達した。
「効率性よりも自分の言葉で書くことに意義があると思う」「生成AIの利用が採用側に伝わって不利になるのではないかという不安がある」といった声が挙がった。
同社では「自分で志望理由を考えなければ、面接で自分の言葉で志望動機を話すことができない」と生成AI活用のリスクを指摘している。
以上
第314話「管理職、女性は12.7%」
企業の課長相当職以上の管理職に占める女性の割合が2022年度は12.7%だったことが厚生労働省の「雇用均等基本調査」で分かった。
過去最高を更新したものの、21年度からの上昇幅は0.4ポイントと限定的で、国際比較では低い水準にとどまった。
22年10月時点で、従業員が10人以上いる全国の企業6000社を対象に調査した。
企業規模別では従業員数が10~29人の企業が21.3%と最大だった。
300~999人の企業は6.2%、1000~4999人の企業は7.2%、5000人以上の企業は8.2%といずれも1割に満たなかった。
大企業における数字でも国際的に低い水準が続いている。
労働政策研究・研修機構によると、21年の日本の女性管理職割合13.2%だった。
スウェーデンは43.0%、米国は41.4%、シンガポ-ルは38.1%と欧米など主要15カ国で最も低かった。
政府は30年までに東証プライム市場に上場する企業の女性役員の比率を30%以上とする目標を打ち出している。
22年からは常用労働者301人以上の企業に男女の賃金差の公表も義務付けた。
厚労省の担当者は「女性管理職の登用は息の長い取り組みであり、引き続き登用率の向上を呼びかけていきたい」としている。
以上
第313話「忘新年会実施予定増」
東京商工リサ-チが都内企業988社に忘年会や新年会について尋ねたところ、56.9%が実施予定であることがわかった。
コロナ禍前に忘年会や新年会を開いていた企業は58.8%で、コロナ禍前の水準にほぼ戻った。
昨年の調査では、39.4%の企業が実施予定と回答していた。
「5類移行」が実施率を押し上げたとみられる。
今年の調査で、「コロナ禍前も実施する」と回答した企業は366社だった。
理由(複数回答可)を尋ねたところ、「従業員の親睦を図る」(83.8%)が最多で、「従業員の士気向上」(52.7%)が2番目に多かった。
「コロナ禍前は実施せず、今回は実施する」と回答した企業は197社。
同社では、リモート勤務の浸透などで希薄になった社員同士の結びつきを強める狙いがあると分析している。
一方、「コロナ禍前は実施していたが、今回は実施しない」と回答した企業も212社あった。
理由は、「開催ニ-ズが高くない」(58%)が最多で、「参加に抵抗示す従業員が増えた」(37%)、「在宅勤務が定着して従業員が一堂に会する機会がない」(17.5%)と続いた。
コロナ禍を契機に方針を変えた企業は、全体の約4割に上った。
同社では「コロナ禍を経て社会情勢や従業員の意識が変わり、各企業が社内コミュニケ-ションのあり方を模索している」とみている。
以上
第312話「子ども預け先、祖父母7割超」
仕事や急用が入ったとき、誰に子どもを預けたらよいだろうか。
女性労働協会(東京・港)が実施した小学校低学年以下の子どものいる保護者への調査によると、子どもを預かってほしいと思ったことがある保護者(1526人)のうち、預け先として「祖父母」を挙げたのは73.2%に達した。
「友人・知人」が17.4%、「祖父母以外の親族」が16.7%だった(複数回答)。
ただ、「預かり先が見つからず自分で子どもをみた」と答えたのも4人に1人の割合に上った。
子どもを預ける際に重視している点は「預かってくれる人が信頼できる」が48.3%で最も多かった。
「利用料金が安い」18.9%や「いつでもすぐに預けられる」の9.8%を大きく引き離している。
同協会では、「不適切保育などが起きている中で、他人に子どもを預けることに抵抗感をもつ人が多いのではないか」と指摘している。
以上
第311話「女性管理職30%、中小少なく」
人材サ-ビス大手のエン・ジャパンの調査で、女性管理職比率30%以上の中小企業は1割にとどまることが分かった。
社内に手本となるロ-ルモデルがおらず、意識改革が進まない実情があるようだ。
調査では、女性管理職比率が5%以下の企業が全体の63%を占め、30%以上は全体の12%にとどまった。
女性活躍推進に向けた課題(複数回答)を聞くと、「社内に女性のロ-ルモデルがいない(少ない)」、「女性社員の意識」がともに45%で最多で、「管理職の意識」が36%と続いた。
評価に性差が出るとの指摘のほか、大手に比べて人員が少なくて業務の分担や代替ができず、責任の重い業務を女性社員に任せにくいとの声もあった。
以上
第310話「仕事と両立、子育て中は緩く」
働く女性(キャリジョ)について研究する「博報堂キャリジョ研」の調査によると、仕事をするときに「出産育児関連の制度が整っている会社で働きたい」と回答した20代女性は70.7%に達し、女性全体(50.5%)を20ポイント以上上回った。
男性でも20代は49.6%となり、全体(36.1%)を10ポイント以上上回った。
若年層ではワ-クライフバランスをより重視する傾向が見られた。
未婚者に聞いたところ、子供が生まれた後は「今より緩いペ-スで働きたい」は20代女性で57.9%で女性全体(49.1%)を上回っている。
一方で、「仕事は辞めて専業主婦になりたい」と答えたのは20代女性で7.7%で全体(11.6%)に比べると低い。
20代男性でも「今よりも緩いペ-スで働きたい」は39.0%と男性全体を7.8ポイント上回った。
博報堂キャリジョ研では「若年層ほど夫婦で一緒に子供を育てたいという傾向がみられた」と分析している。
以上
第309話「中途採用、6割がフリ-タ-も」
深刻化する人手不足において、非正規雇用で働くフリ-タ-を採用対象に加える企業が増えている。
人材サ-ビスのレバレジ-ズ(東京・渋谷)がまとめた調査によると、中途採用で「フリ-タ-は対象者に入る」との回答は65%となった。
「採用対象者ではない」は23.7%、「以前は対象者としていたが現在はしていない」は11.3%だった。
採用対象とする企業のうち、実際に正社員として採用したことがある割合は84.7%に上った。
規模が大きいほどフリ-タ-の雇用実績は高かった。
企業規模1~50人では43.7%だったのに対して、101~500人では64.8%、1000人以上では81.4%に達した。
フリ-タ-の採用を始めた目的(複数回答)について尋ねたところ、「採用数を確保したい」が53.6%で最多だった。
「早急な人員確保を行いたい」39.7%や「人件費を抑えたい」28.9%など人手不足やコスト圧縮に伴う理由が目立った。
人手不足を背景に正社員の採用は競争が激しく、各社では雇用形態を広げた戦略の一方で、派遣社員やアルバイトのほか、副業やフリ-ランスといった外部人材の活用も広がっている。
以上
第308話「社長の平均年齢、平均59.8歳」
帝国デ-タバンクがまとめた「東京都社長年齢分析調査」(2022年時点)によると東京都内企業の社長の平均年齢は59.8歳だった。
全国平均の60.4歳より低かったものの、過去最高だった前年を0.1歳上回った。健康寿命の延びに伴う社長の高齢化が進み、後継者不足による倒産リスクも高まっている。
22年中に社長交代した割合は4.62%で前年から0.25ポイント下落した。
社長引退時の平均年齢は66.0歳で、社長交代による若返り効果は平均12.8歳だった。
年代別では50歳以上が約8割を占め、40歳未満の社長の割合は17年から1.1ポイント減少の4.4%だった。
産業別では「製造」が62.9歳で最も高かった。
一方で参入障壁が低い「サ-ビス」は56.9歳と最も低かった。
「新型コロナウイルス禍で企業が守りに入り、新規参入企業も少なかったため若い社長の割合が減少した」のではないかと分析している。
以上
第307話「女性が感じる職場でのギャップ」
求人検索サイトのインディ-ドジャパンが15歳以上の働く男女5000人に聞いたところ、直近3年で「ジェンダ-ギャップを感じる職場の慣習や暗黙のル-ルがある」と答えた割合が59.8%に達した。
「男性の方が昇進しやすい」(15.8%)、「男性の方が責任ある仕事を任される」(16.5%)、「男性は長期(1カ月以上)の休暇を取得しずらい空気がある」(16.4%)といった声が挙がった(複数回答可)。
「女性が生理で休むとは言いづらい雰囲気がある」は女性に限れば20.3%。男性は5.0%で、その差は15ポイント超と最も大きかった。
こうしたギャップを感じながら指摘できなかったと答えた人に理由を尋ねると、「どうせ変えられないと思った」(45.9%)、「波風を立てたくなかった」(39.7%)が上位を占めた。
この結果から、一社員の行動だけで組織は変わらないという諦めや、同調圧力が声を出せなくさせているのてはないかと分析している。
以上
第306話「今年4%賃上げ企業、来年も3%以上が5割」
外資系コンサル会社のWTW(ウイルス・タワ-ズワトソン)の調査によると、2023年に一般社員の賃金を前年に比べ4%以上引き上げた主要企業のうち、24年も3%以上の実施を見込む割合は約5割となった。
一方、23年に賃上げ率の小さかった企業は24年も賃上げに消極的で、企業間で賃上げの格差が広がりそうだ。
WTWが主要大手169社を対象に調査したところ、23年の賃上げ実績(中央値)は一般社員が3.2%、管理職が2.8%だった。
23年の賃上げ率別に24年の賃上げ目標を聞いたところ、23年に一般社員で「4%以上」の賃上げを実施した企業で24年も「3%以上~4%未満」の賃上げを見込むと答えた割合は39%、「4%以上」は13%だった。
一方、23年の賃上げ率が「2%未満」だった企業は9割近くが24年も同程度の賃上げを見込んでおり、「各社の報酬水準の格差が広がれば、優秀な人材確保を通じて成長が持続する企業と低成長に甘んじる企業の優勝劣敗が広がる可能性がある」と指摘している。
以上
第305話「ク-ルビズ実践、中小は4割」
帝国テ-タバンクの調査(7月7日~11日インタ-ネット1277社から回答)によると、夏の節電対策としてク-ルビズを実践している中小企業は約4割にとどまっていることがわかった。
大企業の7割に比べ大幅に少なかった。
電気料金が高騰する中、効果的な節電対策は急務になっているが、「大企業は社内の制度として取り組むケ-スが多いが、中小企業では社員それぞれの判断にゆだねられる場合が多い」と分析している。
回答結果(複数回答可)
◇ク-ルビズを実践している
大企業・・・70.1% 中小企業・・・44.7% 小規模企業・・・36.2%
◇こまめな消灯を実施している
大企業・・・74.5% 中小企業・・・66.4% 小規模企業・・・66.7%
◇推奨する冷房温度
セ氏26度・・30.7% セ氏27度・・22.9% セ氏25度・・18.7%
以上
第304話「違法残業1万4147事業所」
厚生労働省は全国の労働基準監督署が2022年度に立ち入り調査した3万3218事業所のうち、43%にあたる1万4147事業所で違法な時間外労働(残業)が見つかり、是正勧告を行ったと発表。
調査は、長時間労働に関する内部からの情報提供や、従業員からの労災申請があった事業所などを対象に実施。
違法残業が確認された事業所は、新型コロナ禍で休業する事業所が多かった20年度(8904事業所)、21年度(1万986事業所)に比べて大きく増加した。
22年度に違法残業が確認された事業所のうち、「過労死ライン」とされる月80時間超の残業が行われていた事業所は5247事業所(37%)だった。
月100時間超が3320事業所(23%)、月200時間超も168事業所(1%)あった。
業種別では、小売業などの「商業」が最も多く3291事業所(23%)。
「製造業」が2802事業所(20%)、「接客娯楽業」1491事業所(11%)が続いた。
厚労省では「感染収束に伴い、事業活動を再開させた企業が増え、違法残業も多くなり、長時間残業の解消に向け、企業向けの啓発活動などを強化していく」としている。
以上
第303話「仕事選び社会との接点も重要」
女性はなぜ働き続けたいと考えるのか。
人材サ-ビスのビ-スタイルホ-ルディングスの調査によると、「今後の生活に不安を感じるため」と答えた人が65.2%と最も多く、「社会と関り視野を広げたいため」「旅行や買い物など自分または家族の生活を豊かにするため」と答えた人も6割を越えた(複数回答)。
また、仕事をすることが「好き」と答えた人は77.8%だった。(「とても好き」と「どちらかといえば好き」の合計)。
「対価をもらえることで自己肯定感が高まる」という声や「自分のライフスタイルに合わせて仕事を無理なく続ける職場があれば、長く続けていけると思う」などの意見が寄せられた。
同社のしゅふJOB総研では「金銭面」と「社会との接点」は年代を超えた働く動機であるとし、「求職の際には給与条件とともに、その仕事を通じて社会とどんな接点が生じるかも大切な要素だ」と指摘している。
以上
第302話「副業者6割勤め先に届け出ず」
JILPT(労働政策研究・研修機構)は副業者の就労に関する調査を行った。
18~64歳の就業者159万8770人を対象に行い、18万8980人から有効回答を得た。
仕事を2つ以上持っている副業者は全体の6.0%で、本業の就業形態は非正社員が41.0%で最も高く、次いで正社員が38.1%だった。
本業の勤め先で副業が禁止されているか尋ねたところ、11.0%が「禁止されている」、73.6%が「わからない」と回答した。
勤め先に副業していることを「知らせている」としたのは38.7%、「正式な届出などはしていないが上司や同僚は知っている」が23.8%で、あわせて6割が勤め先に届け出ていなかった。
「知らせいない」割合は正社員43.5%で非正社員31.9%より高かった。
以上
第301話「管理ではなく、遊びの場づくりを」
日本企業は社内で人材を育成してきた。
今のリスキリングとは何が違うのか。
実践共同体やキャリア開発に詳しい法政大学大学院政策創造研究科教授の石山恒貴氏によると「VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)の時代に企業は、短期に変化に応じて、必要なスキルの社内蓄積を目指す。
そのために企業が学び直しを進めるのがリスキリング。
一方、リカレント教育(社会人の学び直し)は個人が主語。
企業がリスキリングですぐに成果を出そうとすると、社員はやらされ感を持つ」「リスキリングを個人の行動と組み合わせれば、社員に自律性が生まれ、実践共同体が有効になる。
社員は専門性が高まると、互いに刺激し合い、学び合っていく。
企業は実践共同体に関与しすぎてはいけない。
成果を求めて管理しようとすると、結局うまくいかない。
かつて日本企業のQCサ-クルと呼ぶ小集団活動が機能したのも社員の自主性を生かしたから」「ジョブ型を導入すれば上手くいくという考え方は単純。
ジョブ型には『テ-ラ-の科学的管理法』の管理重視・創造性軽視の短所があり、欧米企業はその点の修正を進めている。
企業は場づくりをしても、社員の学びの主体性を口に出さないこと。
一見、経営に無駄に思えても、実は遊びこそが大事。
管理ではなく、遊びの場づくりに徹したい。
社員を信じる力が問われる」と指摘している。
以上
第300話「業務の見直し必要」
働く人のリフレッシュや学び直しの時間の確保、子育てや介護との両立などに有効として、「週休3日制」が注目されている。
2022年厚生労働省の調査では、「完全週休2日制」の企業で働く人が全体の60%なのに対し、週休3日制を含め、それより多い人も10%を占めるまでになった。
高齢者の入居施設などは土日も休みではなく、夜勤もあり職員の負担が大きくなりやすい。
介護現場への週休3日制導入は、「2日続けて休みを取りやすくなるなど、職員の負担軽減に有効で、人手不足が深刻な介護業界にマッチしている」との見方がある一方、夜勤時間の短縮や、日勤職員との引継ぎなど新しい働き方への切り替えには業務の見直しと、それぞれの現場の実情に応じた制度設計が必要となる。
以上
第299話「シニア女性のへそくり夫の倍」
シニア女性向け雑誌「ハルメク」が2022年10月、50~79歳の既婚男女600人に実施した調査で、「自分だけのへそくり」があるかとの質問に対し、あると答えたのは夫で36.7%、妻で45.3%だった。
金額を聞くと、妻の平均額は739万円で夫の平均額334万円を大きく上回った。
使い道を聞くと、夫は「自分の趣味に使いたい」が48.2%と多かったの対し、妻は「予期していない突発的な出費への備え」44.1%、「自分の老後の生活費として」39.0%が上位だった。
同紙では、妻のへそくりの多さは、女性の平均寿命が長く、夫の死後の生活への不安が大きいと分析している。
男女とも自分で稼いだお金をためている人が多いが、妻は生活費の一部や親の遺産をへそくりにしている人も多かったと報告している。
以上
第298話「18歳、必ず子を持つは12%」
日本財団が2022年12月に実施した「18歳意識調査」によると、「必ず子どもを持つと思う」と回答した人は12.4%にとどまった。
「多分持つと思う」の33.2%と合わせても半数に届かなった。
「絶対に持たないと思う」9.1%と「多分持たないと思う」13.9%は合わせて2割を超えた。
一方で「将来子ども持ちたいと思う」は35.7%、「どちらかと言えば持ちたいと思う」は22.9%で、合計で6割近くの人は持つことを希望していることも分かった。
子を持つうえでの障壁(複数回答)としては、「金銭的な負担」が69%でトップで、続いて「仕事との両立」が54.3%だった。
いづれも女性が男性を上回った。
7割超の人が少子高齢化に危機を感じており、政府に求める少子化対策(複数回答)は「教育の無償化」が最多で、「子育て世帯への手当・補助金の充実」が続いた。
以上
第297話「春闘賃上げ率の中間集計」
労働組合の中央組織「連合」が今春闘の賃上げ率の中間集計を公表した。
それによると、「定昇相当込み賃上げ計」は加重平均で11,022円・3.69%(昨年同期比4,765円・1.58ポイント増)、うち300人未満の中小企業は8,456円・3.39%(同3,362円・1.33ポイント増)となった。
有期・短時間・契約等労働者の賃上げをみると、加重平均で賃上げ額は時給58.70円(昨年同期比33.18円増)・月給8,897円(同3,313円増)となった。
このまま推移して最終集計で賃上げ率が3%台になれば、平成6年以来の高水準となる。
以上
第296話「男性育休の取得日数9日増」
明治安田生命保険が2022年8月、0~6歳の子どもがいる既婚男女1100人の調査から子どもを持つ男性が、長めの育休を取るようになってきたことが分かった。
育休を取った男性は23.1%で前年調査より3.3ポイント減ったが、取得日数は平均で30日で、前年の平均21日と比べると9日延びた。
社内研修などを通じて子育ての大変さを感じた男性が、長めの育休を望む傾向にあると分析している。
ただ、制度はあるものの、取り易さは企業によってさがあるようだ。
育休を取得していない理由を男性に聞いたところ「給与が減るなど、金銭的な面でとりにくい」(育休未取得の男性のうち21.0%)のほか、「利用するための職場の理解が足りない」(同19.3%)という回答が多かった。
2022年10月からの法改正で「産後パパ育休」制度が始まり、分割取得などで男性の育休取得を促しているが、実際に育休を取るには職場の理解や雰囲気作りが重要となる。
以上
第295話「学生が希望する勤務体系」
就職情報会社マイナビが大学3年生1950人に、週休2日制と、給料が減る代わりに休みが増える週休3日制のどちらを希望するかを聞いたところ、「週休2日制」と回答した割合は68.6%で、「週休3日制」の31.4%を大きく上回った。
学生からは、「物価高で金銭面が不安」や「早くキャリアアップがしたい」などの意見が寄せられた。
「週休3日制」を希望した学生からは、「資格勉強などの自由時間を確保したい」との声も上がった。
調査担当者は、「成長意欲が高く、休みの多さより経済的な自立を求める学生が多いようだ」と分析している。
以上
第294話「オンライン授業の課題」
新型コロナウイルスの流行後に急拡大したオンライン授業について、大学生の4割が「疲労を感じやすい」と捉えていたことが文部科学省の調査(大学生11万人の回答)で分かった。
学生からの発言も可能な同時双方向型のオンライン授業の課題について(複数回答可)、
「他の学生とやりとりしにくい」・・・42%
「映像・音声や通信環境の影響で授業が受けにくい」・・・41%
「疲労を感じやすい」・・・40%
「教員とやりとりしにくい」・・・36%
「レポ-ト等の課題が多い」・・・32%
「授業が理解しにくい」・・・25%
と回答した。
一方で良かった点としては、
「自由な場所で授業が受けやすい」・・・51%
「自分のペ-スで学習しやすい」・・・32%
「レポ-ト等の課題に取り組みやすい」・・・23%
「授業が理解しやすい」・・・20%
だった。
また、生活時間について尋ねたところ、69%の学生が授業期間中に部活動やサ-クルに費やす時間が「0時間」とした。アルバイトが「0時間」も27%おり、コロナ禍の学生が思うように活動できなかったことがうかがわれた。
以上
第293話「日本は子どもを産みやすいか」
子どもは欲しくても、日本社会が「結婚や出産がしづらい」ために不安を感じている20代が多いことが、公益財団法人1 more Baby応援団の調査(20代の男女2478人)で明らかになった。
「日本は結婚しがたい社会だと思うか」との問いに「とてもあてはまる/あてはまる」と答えた人は35.7%にのぼった。
また、「日本は子どもを産みやすい社会だと思うか」という問いに「とてもあてはまる/あてはまる」と回答した人は22.4%にとどまった。
一方で、結婚・出産への意欲は高い。未婚者に結婚したいかと聞くと、73.8%がいずれ結婚したいと回答した。
既婚者を含め「子どもが欲しい」と答えた人も69.3%あった。
ただ、結婚生活を営む上での不安のトップに「子育ての基本的な費用」が挙がるなど、金銭面に不安を抱えている人が多かった。
同財団では「子育て世代が安心して産み育てられる環境や働き方、経済的支援を構築することで、未婚者の精神的不安も払拭されるのでは」と指摘している。
以上
第292話「働く女性の6割が収入増に関心」
人材派遣のスタッフサ-ビス・ホ-ルディングスの調べによると、働く女性の間で新型コロナウイルス禍で収入増への関心が高まった割合は61.8%に上った。
年代別では20~40代で関心が高く、30代が71%と最多だった。「20~30代は結婚や出産などのライフイベントが集中し働き方を見直す人が多く、コロナ禍の不確実性が重なり将来への不安が高まった。」とみている。
収入増に向けて行っていること(複数回答可)を尋ねたところ、「副業・兼業を開始した」(8.2%)や「新たな知識・スキルを学び始めた」(7%)などが上がった。
20代ではいずれの回答も大きく上回った。一方、特に何も行っていないとの回答か7割と最も多かった。
以上
第291話「採用計画達成できず6割」
企業の採用意欲が回復し、学生の売り手市場となっている中、2023年春入社の採用について「計画人数が達成できず募集追加した」企業は35.1%、「達成できなかったが追加募集はしなかった」企業は23.4%と、当初の計画を達成できなかった企業は6割に迫った。
採用活動で苦労していることについて聞くと、「応募数が少ない」と「内々定辞退が多い」がともに55.9%で最も多かった。
募集をかけても十分な人数が集まらず、内々定を出しても辞退する学生が多いことに対する企業の不安が、採用活動の早期化につながっている面がある。
政府や経済界による連絡会議で示されたル-ルでは選考活動の解禁は大学4年6月以降となっているが、面接の開始時期について尋ねたところ、5月頃に面接を始めると回答した企業は86.1%にのぼった。
追加募集をした企業の対策を複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは「個別説明会を開いた」の60%。次いで多かったのが「自社に興味を示すも応募のない学生へのアプロ-チ」で42.5%だった。
従来の一括採用とは異なる採用活動に取り組む企業も増えていて、企業が学生と直接つながる「ダイレクトリクル-ティングの活用」(32.8%)が広がっているほか、若年層に身近な「SNSで告知した」(9.4%)という企業もあった。
以上
第290話「スタ-トアップの就労に好意的」
求人サイト運営のヒュ-マングロ-バルタレントの調査によると、スタ-トアップで働くことに好意的な人材は74%にのぼり、給与よりも自分の能力を発揮しやすい環境や働きがいを求める声が多かった。
好意的な印象の理由としては「急成長中の業界で新しいプロジェクトに取り組める」(18%)、「自分のアイデアを生かして仕事に責任を持って取り組める」(16%)と言った回答が目立った。
全体の中で、スタ-トアップで働いたことがないと回答した人の87%が今後働いてみたいと答え、そのうちの55%にあたる人は「希望する仕事ができるなら現在の給与より低くても入社を検討する」と回答し、中でも1年以内に転職を希望するとした回答も52%に上った。
スタ-トアップで働くことに「ネガティブ」な印象を持つ人は全体の6%と少数だが、「長時間労働」や「将来の不確実性」などをあげる声も多かった。
以上
第289話「テレワ-クは仕事に慣れてから」
学情の調査によると今春入社予定の新社会人でオフィスへの出社をメインに希望する人は5割を超え、テレワ-クを主体とした人の約2倍だった。
仕事に慣れてからとの回答も2割に迫った。
テレワ-クを取り入れながらも上司や同期とのコミュニケ-ションが必要と感じている人が多いようだ。
入社する企業にテレワ-クの制度があった場合、「利用したい」「どちらかと言えば利用したい」との回答は合わせて7割を超えた。
一方、「利用したくない」「どちらかと言えば利用したくない」の合計は7.3%にとどまった。
テレワ-クの実施頻度を尋ねたところ、「週1~2回」が37.3%と最多だった。
「入社後仕事に慣れてから」は18.2%で、業務内容や仕事の進め方を覚える段階では、上司の顔を直接見られないテレワ-クに不安を感じる人が少なくないと分析している。
以上
第288話「入社後のミスマッチを防ぐには」
日本経済新聞社の調査(製造業371社、非製造業547社から回答)によると、入社後のミスマッチを防ぐ対応策として9割近くが「インタ-ンシップに取り組む」一方、入社後に直面する「配属先の確約」や「転勤や単身赴任を強いる人事制度の廃止」を挙げた企業は1割以下だった。
インタ-ンシップの他に多かったのは「自社ウエブサイトの充実」(71.4%)や「女性管理職の増加」「ワ-クライフバランス・健康優良企業認証取得」(ともに41.4%)で、「初任給の上げ引上げ」も3割を超えた。
働き方の自由度を挙げる取り組みも広がりつつあり、「フルリモ-ト、テレワ-ク推進」や「働く場所を限定した職種の設置」を挙げた企業も2割を超えた。
新型コロナウイルス禍の長期化による採用活動の課題については、「対面の採用説明会」(65.3%)や「内定者とのフォロ-イベント」(60%)など、直接学生や内定者と触れ合う機会が設けにくかったという意見が多かった。
以上
第287話「内定受諾の決め手」
リクル-トマネジメントソリュ-ションズが実施した2023年春卒業予定の大学・大学院生に対する意識調査によると、内定受諾の決め手として「自分のやりたい仕事(職種)ができる」を選んだ学生が15.6%と最も多かった。
「社員や社風が魅力的である」(12.3%)を同様の質問を始めた2013年卒以来、初めて上回った。
同社はオンラインでの会社説明会や面接が増えたことで、社員や社風が伝わりづらくなったことが背景にあると分析している。
また、「希望の勤務地に就ける可能性が高い」(11.6%)を選んだ学生が3番目に多く、自分の意思が尊重されることを重視する傾向があることもうかがえた。
自己理解や社会人としての自覚の有無についての調べでは、自分の興味や得意分野・弱みを理解している人は6割前後にのぼった一方、社会人の働き方への理解や社会に出る覚悟などは半数を下回った。
社会人と対話した経験がある学生の方が、自己理解が進んでいることも分かった。
同社は、「企業側も採用活動を通じて学生の自己理解や社会人としての自覚を促すような働きかけが重要で、学生へのフィ-ドバックも有用」と分析している。
以上
第286話「人的資本経営に課題」
人的資本経営への関心が高まる中、適材適所の人事はうまく進んでいるのだろうか。
リクル-トが昨年、従業員30人以上の企業で働く会社員やアルバイトを対象にインタ-ネットで調査(1万459人回答)したところ、「最適な部署だと実感しているか」との質問に「あてはまる」と回答した割合は5.5%、「ややあてはまる」は25.2%で合わせて30.7%にとどまった。
「最適なジョブ・アサインメントだと感じているか」は「あてはまる」が5.9%、「ややあてはまる」が26.8%だった。
また、「スキル・経験等を言語化できるか」との問いに「あてはまる」と回答したのは8%と低く、「ややあてはまる」の33%と合わせても41%で過半に満たなかった。
現状のスキルを可視化することで、仕事のレベルや目標を高めることができるとされるが、多くの働き手がスキルや経験を言語化できず、人的資本投資の効果を最大限にすることは困難と指摘している。
また、企業は今いる人材を最大限に活用しなければならず、管理職とは普段からスキルなどについて対話することが大切になる、とも指摘している。
以上
第285話「都内の中小企業、賃上げ予定なし70%余に」
今春闘が23日からスタ-トしたが、賃上げの動きはどこまで広がるのか。
東京や神奈川に85店舗ある城南信用金庫は、取引がある中小企業738社余りからの聞き取り調査を行った。
それによると、今後の賃上げの予定を尋ねたところ「賃上げの予定がない」と回答したのは537社で、率にして72.8%に上った。
理由としては「業績が改善されず見通しが立てづらい」「仕入れ部品の価格の高騰が著しい」という声があった。
また、「賃上げする予定」だと回答した企業は198社で、26.8%だった。
この企業に対して賃上げ率の見通しを尋ねたところ、1%台が35.4%と最も多く、次いで2%台が27.8%、3%台が13.6%だった。
以上
第284話「遠隔勤務関心あり8割」
大正大地域構想研究所が地方の大学生、大学院生を対象にリモ-トワ-クについて尋ねた調査で、首都圏の企業に遠隔勤務することに「関心がある」との回答が8割近くに上ったことがわかった。
新型コロナウイルス禍を背景に、地元で暮らしつつオンラインを活用した新たな働き方を求める若者が増えたと分析。
地方活性化につなげるためにも、企業とのマッチングが課題と指摘している。
首都圏企業のリモ-トワ-ク正社員としての採用に関心があるとの回答は、「非常に」28.4%と「少し」49.1%を合わせて77.5%に上り、コロナ禍前の2018年調査から18ポイント増加した。
関心の理由は「現居住地に住み続けたい」が35.4%、「出身地に住みたい」が33.1%だった。
リモ-トワ-クの印象は「今後さまざまな分野で広まる」が前回より約29ポイント増の59.6%。
必要な条件として、IT環境やサテライトオフィスの整備に加え「会社と疎遠にならないための社内情報の提供」「社内の人と知り合える仕組み」との回答も目立った。
リモ-トワ-クは「地方に残りたい学生、優秀な人材を確保したい企業、人口流出を抑えたい自治体の3者にメリットがある」と分析している。
以上
第283話「賃上げ実施予定」
日本経済新聞社がまとめたサ-ビス業況調査によると2023年7月までに賃上げを実施する企業が全体の約4割(39.8%)にのぼることがわかった。
サ-ビス業は新型コロナウイルスの影響から回復しつつあるが、人手不足が深刻化しており、賃上げで人手の確保につながる動きが出ている。
その結果、値上げにつながる例もあるようだ。業種別で見ると、クリ-ニング65.2%や理美容57.9%などで賃上げをすると回答した企業の割合が多かった。
背景としてあげられるのは人手不足だ。特にハイヤ-・タクシ-78.6%や、家事支援70.0%などの割合が高かった。
人手不足を解消するためにどのような対策をしているか聞いたところ、「賃上げ」と回答した企業は36.3%に上った。
その結果としてサ-ビスの値上げに踏み切る企業が増えている。さらに、今後1年で値上げする企業も全体の20.5%あった。
以上
第282話「学び直し、教養や収入のため」
ベネッセコ-ポレ-シヨンが学生を除く18歳から64歳の男女3万5500人を対象に「社会人の学びに関する意識調査」をしたところ、学習意欲がある社会人の割合は47%だった。
調査では社会人になってからの学習意欲と学習の有無を調べ、4つに分類した。
「学習意欲なし層」は回答者の41.3%、「学習し続けている層」は33.6%と多かったが、「これから学習したい層」も13.5%おり、唯一女性の割合が半数を超えた。
この層はパ-トやアルバイト、専業主婦が他の層よりやや多く、学習目的は「趣味・教養のため」「収入アップのため」のほか「副業・副収入を得るため」も上位だった。
同社では仕事やキャリアに直結しづらい社会構造があると分析している。
また、リスキリング(学び直し)への注目が高まり、国は重点政策に位置付けており、企業などは学習の必要性を認識して意欲を高めるよう促し、スキル習得ができる環境をつくる必要があると指摘している。
以上
第281話「有配偶者パ-ト女性の6割が時間調整」
野村総合研究所が20~69歳でパ-トとして働く配偶者がいる女性3090人を対象にインタ-ネットで調査したところ、61.9%が働く時間を調整していることがわかった。
就業調整をしている人に年収の壁がなくなったら今より働きたいかと聞いたところ、36.8%が「とてもそう思う」、42.1%が「まあ、そう思う」と答えた。
扶養されている人は年収が103万円を超えると配偶者控除がうけられなくなる。
会社の規模によるが、年収106万円または年収130万円になると社会保険料を負担する必要もある。
政府は10月最低賃金を引き上げたが、時給が上がっても就業調整するため所得増につながらない家庭もあり、共働き世帯の増加など時代の変化に対応した制度づくりを急ぐべきとしている。
以上
第280話「男性育休の転職への影響」
男性育休の環境整備が転職先選びの重要な判断材料になりつつある。
パ-ソナルキャリアが、将来の子育てを希望し、転職に関心のある20~30代の男性200人と、企業の人事担当者200人を対象に調査したところ、双方で7割超が「育休取得実施率の高さは転職時の応募動機に影響する」と回答した。
転職市場における男性育休への関心の高まりは、転職サ-ビス「doda」の求人件数の大幅増の推移からも読み取ることもできる。
今後企業が優秀な人材を確保するためには、「男性育休の意向を含めた転職者のライフプランを知り、主体的なキャリア形成を後押しする視点が欠かせない」との指摘がある。
また、同調査では「今の会社で育休を取得しやすい」との回答は個人・企業共に57.7%だった。
個人の取得意向(90%)とのギャップはまだまだあるが、男性育休を促進する法改正を機に企業の環境整備が進みつつある「明るい兆し」と言える。
以上
第279話「教育訓練投資/若い企業ほど効果大」
IT関連の学習や専門的な資格取得など、企業が従業員に行う教育投資の効果が社歴別に違うことが内閣府の調査でわかった。
創業から27年前後の「若年グル-プ」の企業で教育訓練投資を1%増やすと労働生産性が0.028%高まった。
創業から50年前後の「中齢グル-プ」は0.01%、70年前後の「高齢グル-プ」では0.007%の上昇にとどまった。
ソフトウエアの投資についても、1%の投資増に対する生産性の上昇率は若年が0.019%で高齢は半分以下の0.008%で若年グル-プが高かった。
企業で教育訓練を受けた従業員の割合は経済協力機構(OECD)各国と比べると日本は低く、訓練の普及が欠かせない。
人材投資とともにソフトウエアへの投資も増やせばより生産性を押し上げるため、ソフトとハ-ド両面への投資が重要であるとも指摘している。
従業員自らの自主的な啓発活動は年収増加につながっている。
内閣府が過去1年間に語学や業務改善につながる学習、資格取得をした人の年収を調べたところ学習をしなかった人に比べ30万~40万円ほど高かった。
正規雇用で44万円、非正規雇用で29万円の差があった。
以上
第278話「日本の女性管理職の割合実態」
世界経済フォ-ラムによると、2022年の日本の「ジェンダ-ギャップ指数」は146カ国中116位で中国、韓国よりも下位で、経済協力開発機構(OECD)の統計では日本の男女間賃金格差は加盟44カ国中ワ-スト4位となっている。
男女共同参画の現状は依然として諸外国に比べ立ち遅れており、女性にとって厳しい社会と言わざるを得ない。
なかでも女性管理職の少なさが男女間賃金格差の最大要因と言われ、政府は女性管理職の割合を2020年代の可能な限り早期に30%程度になることを目指している。
帝国デ-タバンクが7月に実施した女性登用に対する見解調査(有効回答企業数1万1503社)によると、管理職(課長相当職以上)に占める女性の割合の平均は9.4%に留まっており、ゼロ(全員男性)が45%を占めたほか、政府が目指す「30%」以上の企業は9.5%と1割にも達していない現状が浮き彫りとなった。
また「女性社長」という視点からは、全国の社長に占める女性社長の構成比は8.4%だった。女性社長の構成比が高い都道府県は、沖縄県11.3%、徳島県11.2%、青森県10.5%と続き、平均を下回ったのは栃木県8.1%、群馬県7.7%だった。
女性経営者と女性管理職の増加と活躍は労働人口の減少対策としても不可欠であり、今後ますますクロ-ズアップされていくと思われる。
以上
第277話「経営者、オフィスの重要性実感」
新型コロナウイルス禍でリモ-トワ-クや在宅勤務が広がったが、オフィスの重要性を認識している経営者も多く、コミュニケ-ション不足や人事評価のしづらさなどの問題を実感する声が多い。
調査会社のネオマ-ケティングが、従業員300人未満で資本金3億円未満の賃貸オフィスビルに入居する全国のスタ-トアップや中小企業の経営者を対象に調べ、1,000件の有効回答を得た。
コロナ禍の2019年12月以降実感したことでは、オフィスビルの重要性を「実感した」「やや実感した」との回答が計46.7%に上った。
「リアルなコミュニケ-ション」では同74%、「リアルな会議」が61.1%とともに半数以上が重要性を実感している。
オフィスビルで働く上でのメリットを聞き取ると「気軽にコミュニケ-ションが取れる」が65.8%と最も多く、次に「業務に集中しやすい」が47.8%、「働くための環境が整っている」が45.5%と続いた。
新型コロナの感染拡大が収束した後にリモ-トワ-クの頻度がどう変わるかについては、「増加すると思う」「やや増加すると思う」との回答が計27.8%、一方で「減少すると思う」「やや減少すると思う」との回答は計32.9%と、減少すると思う方が上回った。
以上
第276話「若手の転職希望者、職場見学を希望」
就職情報サ-ビスの学情は既卒や若手社会人の就職活動の考え方について調査した。
就職活動での選考過程で求める機会を複数回答可の形式で聞いたところ、就業経験3年以上の「ヤングキャリア」では「職場見学」が54.6%と最も多かった。
一方、就業経験のない「既卒」では「カジュアルな面談」が54.7%で最多だった。
同じ20代でも、就業経験によって求める機会が異なることがわかった。
同調査は20代専門転職サイトの訪問者へインタ-ネット上で行い、有効回答数は576件だった。
調査結果はヤングキャリアと就業経験3年未満の第二新卒、既卒に分けて集計した。
以上
第275話「後継者難の倒産 過去最多」
後継者がいないため倒産や廃業をする企業が都内で増えている。
新型コロナウイルス禍に伴う行政の資金繰り支援策で企業倒産件数は低水準に抑えられているが、後継者難による倒産は2021年度に過去最多を更新した。
東京商工リサ-チの調査では、2021年度の後継者難による都内の倒産件数(負債額1千万円以上)は86件だった。
中小・零細企業が中心で、統計を取り始めた2013年度に比べ倍増した。
特に2021年度は前年比で40.9%増え、増加ペ-スが大幅に加速した。
同社によると、新規出店の減少に伴い需要が縮小した建築内装関連が目立つ。
要因別では、代表者の死亡と体調不良が約8割を占めた。
経営者の高齢化は深刻さが増す。
中小企業白書によると最も多い経営者年齢層は2000年は50~54歳だったのに、2015年は65~69歳となった。
2020年も70歳以上の経営者の割合は高まった。
廃業する企業数が高水準で推移しているのは、経済の規模が拡大し続けてきた東京では、事業承継を考えていなかった経営者が地方より多かったことも要因している。
以上
第274話「テレワ-クで夫が家事・育児」
2022年版少子化社会対策白書によると、新型コロナウイルスの感染拡大前後で、夫婦の家事・育児の役割が増加した割合が、テレワ-クの場合で通常の働き方をしている夫の2倍以上に上り、テレワ-クの普及により家庭内の分担を見直すきっかけになったと分析している。
また、夫の休日の家事・育児時間が長いほど、第2子以降の生まれる割合が高くなる傾向があるという。
白書はテレワ-クが少子化対策にも有効とみて、ポストコロナでの継続を求めた。
一方、感染拡大前後で家事・育児の時間の変化については、大幅に増加したと回答した女性の割合が8.7%だったのに対し、男性は3.9%だった。
白書は、在宅時間が増える中、女性の家事・育児の負担がより重くなっている、とも指摘した。
2022年版の子供・若者白書では、2021年に警察が検挙した児童虐待の件数は、過去最多の2174件で、新型コロナの影響により、子供の(地域による)見守り機会が減少し、虐待リスクが高まっている、と警鐘を鳴らした。
以上
webサイトをリニューアルいたしました
業務拡大につき、webサイトをリニューアルいたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。
「TOKYO働き方改革宣言」に弊所の宣言書が掲載!!
「TOKYO働き方改革宣言」の宣言企業に、前田事務所の宣言書が掲載されました。
http://hatarakikata.metro.tokyo.jp/sengen/
働きやすい職場づくりのお手伝いをするにあたり、まずは弊所から率先して宣言いたしました。
これからもよろしくお願いいたします。
事務所移転のお知らせ
謹啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび事務所を下記に移転することといたしました。
これを機に、所員一同決意も新たにより一層の努力をして参りますので、
何卒倍旧のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
謹白
住所
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-24-4 MTビル3階
電話番号
Tel :03-5927-9710
Fax:03-5927-9715
JR 「大塚」駅 徒歩5分
丸の内線 「新大塚」駅 徒歩7分
有楽町線 「東池袋」駅 徒歩9分
都電荒川線 「向原」駅 駅前
JR 「池袋」駅 徒歩15分
webサイトをリニューアルいたしました
webサイトをリニューアルいたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。